【対策】不正アクセスを未然に防ぐ対策方法とは? 見落としがちな課題を解説
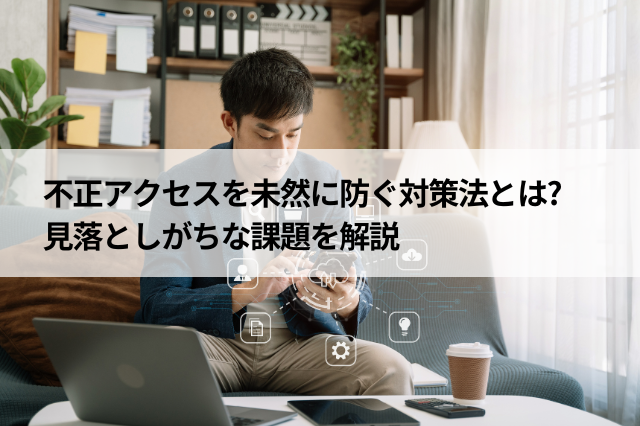

不正アクセス対策は様々な方法がありますが、その対策法は無料で取り組める簡単なものから有料の強固な対策法などがあります。この不正アクセス対策に取り組んでおかなければ、アプリケーションやソフトウェアの重要なデータを書き換えられてしまったり、ランサムウェアというアカウントの暗証番号を書き換えその暗証番号を教える代わりに身代金を要求するウイルスなどに感染してしまう恐れがあります。こういった不正アクセスをされてしまうと、影響が出るのは自社だけではなくお取引先様にも悪影響を及ぼすことになってしまい、信頼関係にも問題が発生してしまう可能性もあります。
こういった問題を発生させないためにも、不正アクセス対策には取り組むべきであり、ITについて詳しくない方でもできる範囲から対策に取り組んでいくべきです。
本記事では、不正アクセスの歴史から解説し最終的には対策方法を解説致します。
目次 不正アクセスとは |
不正アクセスとは
不正アクセスとは、総務省の定義でお話します。
”不正アクセスとは、本来はアクセス権限を持たないものが、サーバーや情報システムの内部へ侵入する行為の事です。その結果、サーバーや情報システムが停止したり、重要情報が漏洩するなど企業や組織の業務やブランド・イメージなどに大きな影響を及ぼします。 顧客情報などが漏洩(ろうえい)すると、その企業や組織の信用が大きく傷つけられてしまうのは言うまでもないことですが、過去には損害賠償にまで発展した事例もあります。 このように、不正アクセスは甚大な被害をもたらしかねません。インターネットは世界中とつながっているため、不正アクセスは世界中のどこからでも行われる可能性があります。” |
不正アクセスの歴史
不正アクセスは、1990年台後半から感染拡大が始まりました。コンピューターウイルスが登場したのは1986年から登場し、初めて作られた目的としてはソフトウェアの違法コピーを検出する目的で配発されました。そのため、コンピューターウイルスは元々実用的な目的で作成されており、今と全く異なる形で存在していました。
そこから数年後、モリスワームというウイルスが多くのコンピューターに感染し多くのユーザーに混乱を与えました。ここから世間的にもウイルスの脅威が広がっていったわけですが、次に多くのユーザーが感染してしまったウイルスが「ランサムウェア」です。
ランサムウェアとは、コンピューターに不正アクセスしフォルダーやアプリケーションを暗号化し、ユーザーに対してパスワードを教える代わりに身代金を要求するコンピューターウイルスのことです。このランサムウェアは、インターネットが普及する以前と以降では感染経路が違っており、インターネットが普及する以前はコンピューターユーザーにフロッピーディスクが配られ、そのフロッピーディスクを通して感染していました。
その後、インターネットが普及すると、利便性が上がるのと同時に不正アクセスの被害件数も大幅に増加しました。今では、テレワークが普及したことでセキュリティの脆弱性を狙った不正アクセスやメールやウェブサイトから不正アクセスされたり、様々な場所からの不正アクセスが増加しています。
| 不正アクセスに関する年表 | ||
| 年代 | 出来事 | 詳細 |
| 1986年 | ブレインウイルス | 初期のコンピュータウイルス。パキスタンのアルビ兄弟によって作成 |
| 1988年 | モリスワーム | 世界初のインターネットワーム。約6,000台のコンピュータに感染。 |
| 1989年 | PCサイボーグ(AIDS Trojan) | 世界初のランサムウェア。フロッピーディスクを通じて配布。 |
| 1998年 | 不正アクセス禁止法 | 日本で成立。不正アクセス行為やその助長行為が違法に。 |
| 2000年代 | コードレッド、ニムダ | インターネットの普及に伴い、さまざまなウイルスが広がる。 |
| 2010年代 | フィッシングメール、ランサムウェア | 標的型攻撃が増加。 |
| 2020年代 | テレワークの普及 | セキュリティの脆弱性を狙った攻撃が増加。 |
不正アクセスの被害件数
不正アクセスの被害件数は年々増加しており、中でも法人の被害件数が最も多いのがランサムウェアです。独立行政法人情報処理推進機構(通称IPA)の調査によると、令和2年の下半期のランサムウェアの被害件数が21件だったのに対し、令和6年上半期の被害件数は128件と約6倍の被害件数となっております。主なランサムウェアの侵入経路としては、VPN機器とリモートデスクトップ(VDI)が大半を占めており、遠隔地で作業をする際のセキュリティの脆弱性を狙った不正アクセスが多い印象にあります。
参考情報:マルウェア「ランサムウェア」の脅威と対策(脅威編) 警視庁
不正アクセスの原因
不正アクセスの主な原因としては2つあり、それがセキュリティの脆弱性を狙った不正アクセスとフィッシングメールやウェブサイトからのウイルス感染です。セキュリティの脆弱性を狙った不正アクセスに関しては、セキュリティ担当者の徹底的なセキュリティ対策必要になってきますが、2つ目のフィッシングメールやウェブサイトに関しては誰でも注意すれば不正アクセスを未然に防ぐことが可能ですので、まずは見知らぬメールやサイトは開かないことが不正アクセスの対策になります。
不正アクセスの対策法
これまで、不正アクセスの様々な側面について解説しました。ここからは不正アクセスされないためにはどのような対策が必要なのかを解説します。
多要素認証/二要素認証を取り入れる
不正アクセスを防ぐために、最近多くの企業で導入されているのが多要素認証です。多要素認証とは、「知的情報」や「所持情報」、そして「生体情報」の計3つの要素のうち2つ以上を組み合わせて認証する方法のことを指します。この多要素認証と似たもので、二段階認証というものがありますが、二段階認証と多要素認証は別のものになっております。具体的に説明しますと、二段階認証というのは、「要素の組み合わせは必要無く認証を2回行うこと」ですので、要素を複数組み合わせなければならない多要素認証とは別のものという訳です。
多要素認証を導入する最大のメリットは、第三者からの不正アクセスされるリスクを大幅に削減できる点です。その理由は、ID・パスワードという知的要素だけではログインできなくなるからです。そもそも、なぜ多くの人が不正アクセスの被害者になるかと言うと、簡単なID・パスワードで様々なアプリケーションやサービスに登録してしまい、外部に情報が漏れてしまうことが多くの理由です。多要素認証であれば、ID・パスワードがばれてしまったとしても、その知的情報以外の要素が漏洩しなければ不正アクセスできません。
こういった面から、多要素認証は世界的に重要視されており、多くの企業で導入が進んでおります。不正アクセスを防ぎたい方はぜひご検討ください。
ID・パスワードの使いまわしを控える
ID・パスワードを固定して様々なサービスで同じものを利用してしまうと、不正アクセスのリスクは大幅に上昇します。その理由は、ID・パスワードを使い回してしまうと、どれか1つのアプリケーションやサービスで流出してしまった場合、すべてのアプリケーションやサービスでも情報が流出してしまうからです。警視庁の調査によると、不正アクセスの手口の最も多い理由がこのID・パスワードの流出になっており、全体の90%を占めております。また、この90%のうち40%がID・パスワードを使い回し知らぬ間に流出してしまっております。そのため、アプリケーションやサービスを運用する場合は、それぞれ違ったID・パスワードの設定をおすすめします。そして、無料で取り組めることなので、是非ご検討ください。
参考情報:不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況.pdf
不審なメールや怪しいサイトは閲覧しない
不正アクセスの被害として二番目に多い侵入経路が、不審なメールや怪しいサイトから侵入される「フィッシング」となっております。最近では、多くのメディアが取り上げたことで知っている方も多くいらっしゃると思いますが、まだまだ被害件数は多いようです。また、年々巧妙な手口でID・パスワードを聞き出そうとする手段が増えてきていますので、身に覚えのないメールやサイトはもちろんの事、少しでも違和感があったり変にID・パスワードを聞き出そうとしてくるメールやサイトには気を付けましょう。
見知らぬフリーWi-Fiには接続しない
街中でフリーWi-Fiを提供しているスポットなどを見たことがありますでしょうか。実は、このような見知らぬフリーWi-Fiにも不正アクセスのリスクが潜んでいます。その理由は、Wi-Fiに接続された場合に第三者からデバイスの情報を覗き見することが可能だからです。仮にWi-Fiに接続してしまった場合、ID・パスワードが盗まれたりコンピューターウイルスを流し込まれたりしてしまいます。こういったウイルスに感染してしまった場合、自分だけではなく周りの関係者にも影響を及ぼす可能性が非常に高いですので、十分に気を付けましょう。
最後に
不正アクセスは、私たちの身近に潜んでいるものであり多くの人が対策する必要があります。その対策法は、無料で簡単に取り組めるものからお金をかけて厳重に対策するものまで様々な物があります。その中で、どういった対策に取り組んでいくのか、どのようにして対策するのかは自分に合ったものを選ぶのが最適です。これまで被害にあったことが無い方でも、明日には不正アクセスの被害者になっている可能性も十分にあります。簡単なところから不正アクセス対策に取り組んでいきましょう。
関連記事
■【わかりやすく解説】多要素認証(MFA)とは イラストを交えて解説!
■【目的】多要素認証の目的を解説 多要素認証が求められる背景を解説
■中小企業にDaaSを導入したいならアプリップリ DX Proがおすすめ
■リモートデスクトップとは? 法人向けオススメサービスはアプリップリDX Pro

